 |
|
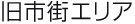 |
|
 |
|
明暦元(1655)年の移転時に、白山神社から、南北約2.1キロ、東西約0.5キロの細長い形で町割りが行なわれました。それが現在の古町・本町1〜9エリアで下町(しもまち)エリアの一部で、道路は碁盤の目のように規則的です。
町建てのとき、信濃川から堀を引き込み、南北方向には西堀・東堀を、東西方向には白山堀・新津屋小路堀、新堀、広小路堀、御祭堀をつくりました。西堀の海側には奉行所や寺院が配置されました。その界隈は寺町として現在も往事の名残を残しています。
堀は戦後順次埋め立てられ、昭和39(1964)年の新潟国体までに現在の姿になりました。堀を埋めてつくられた道路には、かつての堀の名前がつけられています。南北方向の道路は「○○通り」、東西方向は「○○小路」としています。
このエリアは江戸時代以来、船運が鉄道に取って代わられるまで湊町として栄えた町にふさわしく、廻船問屋や網元屋敷などの町屋が残されています。
さらに北側(信濃川河口寄り)の下町エリアは明治以後にモザイク状に開発され、迷路のような路地が特徴です。 |
 |
|
 |
|
 |
|
お座敷で芸妓の芸を楽しめる店がある街を花街といいます。かつては全国各地に花街がありました。
新潟町でも江戸時代から町のあちこちで花街が栄え、文人墨客や政財界の有力者が集まりました。江戸時代後期には新潟芸妓は芸の質の高さで全国に知られた存在でした。
古町花街は、明治の初めにつくられた東新道(鍋茶屋の前の道)から始まりました。が、明治26(1893)年の新潟大火で古町花街は焼失しました。それを契機に花街の中にあった遊郭が移転し、古町花街は一時はさびれたといいます。
しかし、大火後に整備された西新道・東新道に沿って、料亭や茶屋(貸座敷。料理は出さない)、置屋(芸妓が籍を置く家)などが軒を連ねていき、やがて古町花街は芸の街として再生しました。
その後この界隈は大きな火災などがなく、戦前に建てられた建物が数多く残されることになりました。
町建て以来新潟町を縦横に走っていた堀は戦後順次埋め立てられ、町並みは様相を変えていきました。かつて古町を賑わせた劇場や映画館も姿を消しました。が、古町花街は、変転激しいメインストリートの古町通りから一歩入った奥深くで、懐かしい町並みの名残を今に留めています。
全国で花街が姿を消したなか、古町花街は今も芸妓が活躍するだけでなく、伝統ある建物を使いつづける店が並ぶ、生きた花街です。
花街建築の見どころ
町屋とは異なる華やかな造りが特徴です。
建物は道路に直接接しておらず、塀で囲まれた前庭や玄関へのアプローチがあり、奥まった印象があります。屋根は寄棟や入母屋を用いて豪華に造っています。細部にも数寄屋風のデザインが施され、たとえば張り出し2階の、張り出し部分の上げ裏を曲面状に仕上げています。建物の中も銘木を使ったり、それぞれの座敷でデザインのテーマを変えるなど趣向が凝らされています。
|
 |
|
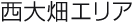 |
|
 |
|

新潟島は日本海に沿って小高い砂丘が伸びています。砂丘と町のあいだの地域は江戸時代以来「寄居村」と呼ばれ、幕末には畑地が広がっていました。
明治以後、この畑地と砂丘の高台は文明開化の地として開発され、学校や病院などが建設されました。官立師範学校(明治8/新大医歯学総合病院)、新潟医学専門学校(明治43/同)、明治41年に焼失した師範学校の新校舎(明治43/新大医学部保健学科)、旧制新潟高校(大正11/新大付属小・中学校)などです。
重厚なデザインの木造洋風の校舎は、この地域に、旧市街にはない西洋文化の雰囲気を吹き込みました。
 開発が進むにつれ住宅建設も始まりました。良好な住宅を求める新潟市内外の富裕層が高台に本邸や別邸を構え、また官舎も建てられました。これらに、和風ですが接客部分を洋風につくる家屋が登場しました。旧知事公舎(明治42/昭和63年に新発田に移築) は和館と洋館が独立する並列型、副知事公舎(大正10/現・ネルソンの庭)、市長公舎(同/現・安吾 風の館)は和館に洋館が付属する「洋館付住宅」の初期のものです。
開発が進むにつれ住宅建設も始まりました。良好な住宅を求める新潟市内外の富裕層が高台に本邸や別邸を構え、また官舎も建てられました。これらに、和風ですが接客部分を洋風につくる家屋が登場しました。旧知事公舎(明治42/昭和63年に新発田に移築) は和館と洋館が独立する並列型、副知事公舎(大正10/現・ネルソンの庭)、市長公舎(同/現・安吾 風の館)は和館に洋館が付属する「洋館付住宅」の初期のものです。
こうしてこの地域には、旧市街とは趣のことなるハイカラな町が誕生しました。 |
 |