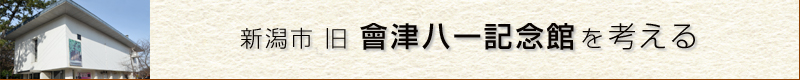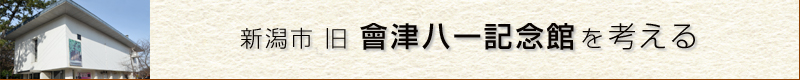會津八一記念館館報 第2号 昭和52年11月21日

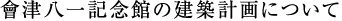
長谷川建築事務所
所長 長谷川洋一
新潟市の西半分は、信濃川と日本海とに囲まれた帯状部分で、海岸線に近い部分は、信濃川の運んできた土砂と季節風とによって出来たであろう砂丘地帯からなっています。現在は、海岸線の発展により、大分少なくなりましたが、それでも昔ながらの美しい松林とアカシア林に面する、角に此の建物の敷地があり、付近一帯は低層な住宅地域で、位置的には、新潟市の中心よりごく近い距離にあります。
敷地は約三百坪程度で、三角状をなし、三方道路で、路面より、若干低い松林の中にあります。敷地について先づ考えられることは、異形で、高低変化ある現状を如何に利用するかという事で、先づ既存の樹木をできるだけ伐採せずに建物を配置することから始まり、且つ四季を通じて変化する広大な松林側の眺望を如何に多く建物内部に取り入れるかにありました。此の為には、建物を先づ海岸線に平行に配置し、アプローチは、それに直角な道路側より出来るだけ後退して、駐車場のスペースにあてると共に、樹木の保存に当る必要を感じました。又、敷地の高低変化につきましては、ボーリングの結果、固定地盤もかなり低いこともあり、埋め戻し等は行なわずに、高床式については、通風乾燥等では利点ですが、何よりも限られた予算内では、それだけ建築費が高くなり、又、他方冷暖房設備の面からは、マイナスの面もありましたが、総合的な見地からあえてこれにふみきった次第です。
建物自体について言える事は、此の記念館が、故會津先生の貴重な遺品の収納庫であると同時に、これを一般に展示するかにありました。それには基本概念としては、耐震耐火で、美術品を永久安全に保存し得る現代建築である事は勿論一般の人々にいかに此の建物の印象をいだかせることと、限られた面積の建物にのスペースに出来るだけ多くの作品を展示し、収納し、且つ出し入れも容易で、貴重な価値のある品物を永久保存し得る様にし、又、外気温や、湿度の変化に充分耐え得る必要もありました。特に収納品の性質上、あまりにも電気空調建築科学的にたよるよりも或る程度は自然的な法則により保存されねばならぬ事も感じました。
外観としては、此の建物が、會津先生の作品の収納展示のみを行い、それ以外の用途は無いとのことで、当然それにふさわしい力強さと格調高い事が望まれると共に、敷地周辺の自然環境に対して違和感のない様心掛けた次第です。それには外壁の大半を日本古来の漆喰色の感じに近いものとし、軒先の黒、及び軒の出の深さと、二階部分のせり出しにより重厚さと陰影を強調する様考慮した心算です。又、もう一つ新潟地方では厄介な問題がありました。それは、一時的にかなり苛酷な気象条件下にあることで、特に海岸に面する建物敷地は、四季を通して潮風の影響をうけ、特に晩秋から春先までの冬期間においては、塩分を含んだ風雪が建物をどこまでもいためつけずにおかない事であります。此の為には、特に良質で、且つ強度あるコンクリートの施工が要求されましたし、腐食する金属等の使用は、極力さけ特に展示室収納庫等は、壁厚を厚くすると共に、ダブル壁方式とし、コンクリートの乾燥養生も充分期間をとりました。
建物内部の構成につきましては、アプローチからの玄関ホールにより、一階事務室、収納庫、図書、談話室部分と、吹抜ホールよりの階段により、二階展示室とに二分しています。一階諸室については、原則として、一般観覧者に開放しないので、受付から直接二階へ上るような動線となっています。二階展示室の展示方式は、壁面を利用したガラスケースと中央展示ケースよりなっています。壁面ガラスケース展示方式は、ガラス面に対する影の問題があり、此の種の配列方式で此を全くさける事は、不可能でありそうかといって露出展示方式では、維持管理の面で問題もあるので、電気設備の面で出来るだけのことはしたつもりです。展示室は大半を自然色に近い、ややあかるい色調とするの共に、室の大きさの点から吹抜等により、室のボリュームを強調する様つとめました。一階諸室については、先に述べた通り四季の新潟海岸の眺望が出来る様ガラス面をとり、二階のせり出しにより、ガラスに対する気象条件よりの保護をはかった次第です。空調設備につきましては、展示室、収納庫。及び其の他に三分して系統を作り、特に前記二室につきましては、恒温恒湿とし、熱源については、都市ガス利用で保守運営の面からの省略化もしています。建物管理については、出来るだけ最少の人数で保守管理されるとの事で、一般事務室で受付、事務、電力、空調設備等のリモートコントロール、及び防災、其の他一切をまかなえるよう計画しました。

*<海岸林>という敷地環境に配慮して、既存樹木を保全し、それらとの調和と「力強さと格調」を意識したデザインを意図したこと。厳しい気候条件に耐え、美術品を「永久保存」する耐震・耐火・耐朽に配慮したこと。一階諸室に「広大な松林の眺望」を取り入れたことなど「風土に配慮した現代建築」を作ろうとした意図が述べられている。 |
|