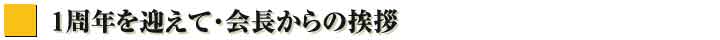 |
| |
|
新潟まち遺産の会も、今月で創立1 年になります。
公開講座と2 回のシンポジウムの開催、副知事公舎の保存要望書と活用案の提出などのほか国際都市政策会議や萬代橋景観フォーラムへの参加など、催しに力を注いだ1年でした。このほか町屋マップの制作、登録文化財の登録手続の支援も進行しています。近く成果や結果がお見せできると思います。
中心となる世話人はいずれも、多忙な仕事を抱えています。そのなか毎月1回の世話人会のほか、メーリングリスト等による意見交換で、いろいろなことを議論し、決めてきました。それぞれ熱い情熱で会の運営に取り組んでいます。今後は一般会員の方々にも、活動により関わっていただける運動の形を考えていきたいと思います。
「まち遺産」という言葉は、当会の造語ですが、早くも定着し始めたような感じがあります。しかし今の時代、「まち遺産」は町の中でつねに存亡の危機に瀕してもいます。会を立ち上げてからも、多くのまち遺産が壊され、また壊されそうだとの情報もしばしば寄せられてきました。当会が所有している明治の町屋の解体部材の活用という課題もまだ未解決です。
世話人と会員の皆様で議論を深めながら、もっとまち遺産がまち遺産として認知され、大切にさえる環境作りにさらに努力していきたいと思います。(大倉宏)
|
|
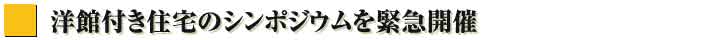 |
|
|
|

会報2号でお知らせしたように、新潟県副知事公舎が問題を抱えています。そこで、その価値を市民に知っていただくため、当会が主催、都市環境デザイン会議(新潟)・にいがた寺町の会・NPO 法人新潟水辺の会・NPO 法人まちづくり学校が共催して、4 月10 日(日)、新潟町建て350 年記念シンポジウム第2 弾「欧風浪漫漂う異人池西大畑界隈と洋館付き住宅の魅力」を、新潟市市長公舎で開催しました。
会場は100 名を超える大盛況となりました。長谷川久彦氏が大畑界隈の風景絵画20 点程を展示され、シンポジウムに色を添えてくださいました。
シンポジウムに先立ち、午前中に大畑界隈町あるき会がありました。予定を超える人数が集まり、2 班に分れて行いました。いつも見ている風景なのに知らない所が見つかったという感想をいただきました。
シンポジウムは、初めに、新潟大学都市計画研究室の今井亜也子氏より、異人池・西大畑界隈のまち遺産と洋館付き住宅の報告がありました。
下町-下本町一帯、西大畑・二葉町・旭町、万代橋一帯に現存する洋館付き住宅を紹介し、特徴として洋館が急勾配の切妻屋根であり、妻面を通りに向けていること、洋館は通り側に建てられていること、洋館付き住宅普及の背景には、大正末期からの洋風志向、文化生活を取り入れた開発業者による文化村の開発などがあることを説明、課題として住民の高齢化、建物の維持、生活環境の問題をあげられました。
引き続き、兼弘彰氏による「横浜に残る洋館付き住宅の保存活用と教育プログラムについて」と題した基調講演が行われました。概要は以下の通りです。
洋館付き住宅は、1920 年代(昭和初期)全国各地に数多く建てられた、和風住宅の玄関脇に洋間(応接間)が付いた建物で、「中廊下住宅」と呼ばれている。その原型は旧岩崎邸で、1896 年(明治26 年)三菱財閥の三代目岩崎久弥が、ジョナサン・コンドルに設計を依頼した住宅である。
横浜市内の鶴見区・神奈川区・保土ヶ谷区などは通勤サラリーマン世帯が多く、その住宅景観は敷地面積100坪以上が多く、庭木が豊富で生垣もあり、ゆったりした空間を持つ。だが平均的な住宅寿命は30 年程度である。
保存するには、リサイクル可能な自然素材、ライフサイクルコスト、技術と文化の情報を持ち、保存改修の手法を学ぶことや、悪い所を調査して間取りを改善したり、価値ある部材の再利用を考えたり、庭木・生垣を残すことが必要である。
最後に、活用の手法や、今後の課題と展望を述べ、同氏がまとめた「横浜に残る洋館付き近代住宅-住まいづくりの生きた教科書」の資料で洋館付き住宅の魅力を語られました。
そのあとパネルデェスカッションに移り、パネラーとして兼弘彰氏と、地元から小山芳寛氏が紹介されました。
大倉宏コーディネーターより、県副知事公舎の現状と、公舎保存活用案を県に提出した報告があり、洋館付き住宅と町並み景観について、まず小山氏にご意見をうかがいました。小山氏は、市山流(日本舞踊の流派)を新潟市の無形文化財第1 号に導いた経緯などを語ったのち、「大畑界隈に住んでいるが、県副知事公舎についてはあまり考えていなかった。自宅は旧日銀支店長宅・新潟市市長公舎と並んだ町並みの中にあって洋館造りの一つである。多くの人が関心を持つように新潟の良き物を大切にしたい」と述べられました。
兼弘氏は、「午前の大畑界隈町あるき会では、非常にまとまった良い環境と洋館付き住宅の見事さに驚いた。独立型の洋館部分の屋根が自然条件に対応して出来ていて、横浜のとは造りが違う。県副知事公舎の今後は、課題と展望を市民の側から掘り起こす必要がある」と発言されました。
ここで篠田昭新潟市長が飛び入りで参加、「旧日銀支店長宅・新潟市市長公舎・小澤邸の活用を含め、昔の物・新しい物の価値を充分把握し定着させたい」と言われて会場を後にしました。
時間の関係から質問時間が足りないなど残念なこともありましたが、盛況のうちに終了しました。県副知事公舎をはじめ、明治・大正・昭和初期の建物や環境への関心が高いことに驚きました。(武蔵靖之)
 |
保存要望書を提出
副知事公舎の保存と活用を求めて、当会では2月14日(月)に県に活用案を提出したのに引き続き、市にも7月11日(月)、他の5 団体との連名で保存活用要望書を提出します。
今後の動きについては、これからも会報等でお知らせしていきます。 |
|
|
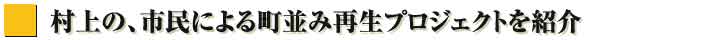 |
|
|
|

去る1 月23 日(日)午後2 時から4 時30 分にかけて、「市民による町並み再生プロジェクト〜城下町村上の挑戦」と題して、新潟まち遺産の会設立記念シンポジウムを開催しました。
これは、新潟町建て350 年記念イベントの第1 弾でもありました。会場の新潟市中央公民館には、約130名の方がお集まり下さり、これまでのイベントの中でも、特に盛況でした。県外からの参加もあり、行政や専門家の参加が多かったのも特徴です。
今回の企画は、「むらかみ町屋再生プロジェクト」を応援し、また村上の取り組みから学ぼうという趣旨でした。このプロジェクトは、市民の寄付をもとに基金を設立し、そこから伝統町屋の外観整備に対して補助金を交付するという、全国でも恐らく初めてのユニークな試みです。都市計画道路問題に揺れ、行政が足踏みするなか、市民自らの力でまちを活性化しようという画期的な挑戦です。既に2 件の再生が完成しています。
プロジェクト会長の吉川真嗣氏からは、実行に至った経緯など全体的なお話を、小池昭雄氏からは、具体的な設計についてのお話を伺いました。またパネリストには篠田市長にも加わっていただき、熱気に包まれた2 時間半でした。当会としては、今後も村上の取り組みを応援していきたいと思いますので、皆様のご協力をお願い致します。
なお、村上のプロジェクトについては、当会ホームページにリンクがありますので、是非ご覧下さい。(岡崎篤行) |
|
 |
|
|
|
近江八幡市の堀の風景
日本の真ん中4 県(福井、岐阜、三重、滋賀)で「共和国」を構成し、順番に「文化首都」を置いています。今年は滋賀県が当番となり、近江八幡市で堀割サミットが5 月14 、15 日に開催されました。初日に水郷めぐり、町並み散策。2 日目は「堀割協議会設立総会」と「水辺から未来へ」というテーマで講演がありました。
「八幡堀」から琵琶湖の内湖「西の湖」へ日本一遅い乗り物=和船に乗って水郷をめぐり、その後、古い商家が残る町並みを散策しました。黒塀ではないが、板塀に見越しの松、うだつの防火壁。堀に商家の町並みが本当にしっくりと落ち着いた風情を醸し出しています。堀を残さなかったら、なし崩しにこの町並みも残らなかったでしょう。
「無くなる」という時に堀と町の歴史を見直し、堀を残す事に頑張った。だからこそ、今この景観となっています。
堀を持つ他都市の事例も紹介され、それぞれに堀と町並みが美しいのですが、しかし新潟は? と振り返ってみれば、すでに堀はありません。古くからの町家や商家も、住民自らの歴史と誇りを見出せないため、バラバラな景観を呈しています。まして、かつての上大川前の商家は櫛の歯が欠けたように安い駐車場になっています。
堀を再生しようという動きは賛成ですが、堀だけではだめで、周辺の景観も一緒に考えていかなければならないと思います。かつては北前船で繋がった都市ですが、この違いは何だろうと考えさせられました。(高橋照子)
|
|
 |
|
●
|
|
いよいよ町屋ショップマップ(仮名)制作も最終段階に入りました。名称も「MACHIYA MAP 」となります。町屋のみを取り扱っているわけではないのですが、やはり歴史ある建物を一言で表し想像してもらえる言葉、それは「町屋」だと思ったからです。
町屋を改造活用した店舗の他、蔵を改造活用した店舗や置屋を再活用した店舗、老舗店舗なども掲載する予定です。マップを開き古い建物を探しながら町歩きをする時に、往時を偲ぶことができるよう堀割の跡を表示したり、町建て時の街の位置などを表示したりもしています。従来沢山ある町歩きマップとはひと味違った物にできあがるはずですので、乞うご期待を!
ところで「あの物件も入れよう」「あの物件入れてた?」など、取材を終えた編集段階でも追加物件がありました。明らかにマップに載せるべき物件でも、こちらの情報不足等で取り扱ってないものもあるかと思います。そういった所も版を重ねる中で付け加えていきたいと思っています。そうした情報も受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。
現在、7 月の出版に向け、急ピッチ制作中です。今しばらくお待ちください。(伊藤純一)
|
|
 |
|
●
|
|
新潟市西大畑、どっぺり坂の階段を上ると、旧日本銀行新潟支店長役宅のお屋敷があります。昭和8年の完成から平成11 年まで、30 人の歴代支店長が暮らしました。
平成12 年から新潟市所有の歴史的建造物として一般公開されていましたが、今年4 月から改修工事に入り、7 月に再オープンの予定です。
新しい支店長宅は市民の文化施設として、お座敷をお茶会や会合等に利用できるようになるほか、蔵がギャラリーになり、美術展やイベントなどの催しが行われます。また、応接間として使われていた洋室では、コーヒー、抹茶などの喫茶を楽しむこともできます。
入場は無料で、いつでも見学できます(月曜休館)。
古くて新しい、市民の憩いの場として、ぜひ訪れてみたいですね。(越野泉)

|
|
 |
|
|
当会の会員で市内にお住まいの渡辺馨一郎さんから貴重なアルバムをお借りすることができました。長年にわたって新旧の新潟の町と建物を写した写真アルバムです。今後シリーズで、このアルバムから新潟の建物の新旧の姿をご紹介していきたいと思います。
今回取り上げたのは、本町14 番町にあった遊郭の水田楼です。この一帯はかつては新潟最大の歓楽街でした。水田楼は5 年前には解体され、今は駐車場になって往時の面影をとどめるものは何もありません。
写真左上は在りし日の水田楼(左側に写っている看板には「菊屋家具本店」とあります)、右下は凝った造作の入り口です。右上は解体直後の様子です。
|
|
 |
| |
|
5 月22 日、新潟市歴史博物館(みなとぴあ)旧第四銀行住吉町店において2005 年度年次総会を開催し、無事終了しました。出席者は30 人でした。2005年度の決算報告は別表のとおりです。
総 会の後で行われた記念講演会では、三つの講演がありました。
「新潟県における市民による歴史的建造物の公開活用」(長谷祐子氏)は、市民やNPO が運営している三条市の丸井今井邸と鍛治町の家が紹介されました。
「歴史的な建物の修復と活用を考える-近代建築、近代産業遺産の保存にあたって」(木村勉氏)は、ドイツを中心にした歴史的建築物の活用の例が報告されました。
「産業遺産の活用に関する事例報告-建築修復学会の活動から」(筑波匡介氏)では、群馬県館林市の正田醤油の建物の修復についての紹介がありました。
|
2005 年度収支報告
|
収入の部
|
|
支出の部
|
繰越金* 108,124
会費 240,000
寄附金 036,940
売上 053,000
事業収入 120,000
|
|
印刷費 070,580
会議費 011,600
交通費 040,810
謝金 012,000
消耗品 029,153
施設使用料 003,500
資料作成費 011,399
通信費 107,655
払込手数料 004,990
次年度への繰越 266,377
|
|
|
|
| 収入合計 558,064 |
|
支出合計 558,064 |
|
*繰越金は「町屋を生かす会」からの繰越金。
|
|
 |
|
|
会報3号をお届けします。第2号から半年以上間があいてしまいました。今号から、会員の渡辺さんからお借りした写真を紹介するシリーズがスタートします。懐かしい写真が次々と出てきますのでご期待ください。写真をみての感想もお寄せください。
編集部では皆さまからのご意見をお待ちしています。資料などもぜひ紹介していきたいと考えています。一人一人がもつ記憶や知識を共有することで、これまでみえなかったまちの姿がみえてきて、新たなまち遺産の発見につながるのだと思います。(千早和子)
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
■ 会報バックナンバー ・・・vol. 1 / vol.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |

