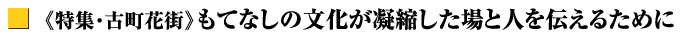 |
|
|
|
当会では、古町花街(かがい)プロジェクトを昨年から本格スタートさせました。古町花街を重要と考える理由は、主に二つです。
第一は、花街があらゆる日本文化を継承している希有な所だからです。
料亭などの日本建築、床の間に飾られる書画や骨董品、そこで提供される日本料理・日本酒、女将さんや芸妓さんの和装、お座敷で披露される邦楽・邦舞、花柳界の人達が身につけている茶道、華道、香道など、すべてが「和」なのです。
それぞれ個別の取り組みはありますが、すべてを一体に継承している場所は、花街以外に見当たりません。花柳界は、日本人を代表して日本文化を残してくれているのです。
第二は、これほど伝統的な花街空間が残っているところは、京都、金沢と新潟・古町くらいしかないからです。
東京には六花街がありますが、空襲後の再建です。盛岡や山形などの地方都市には戦前の料亭建築が残されていますが、古町ほどの集積はありません。古町花街は、新潟が他都市に自慢できる貴重な「まち遺産」なのです。
しかし、地元市民の間でさえ、花街や古町のことは十分理解されていません。当会では、今後も市民の財産である古町花街が多くの人に利用され、末永く存続するよう活動を続けて行きたいと思います。(岡崎篤行) |
|
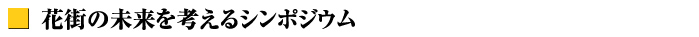 |
|
|
|
 |
| シンポジウムの様子。左から、岡崎副代表、寺田弘さん、市山七十世さん、大倉代表。 |
9 月25日(土)に、三業会館にて、第2回柳都新潟・古町花街シンポジウムを開催し、約60名の参加がありました。
基調講演には(株)粋まち取締役、寺田弘氏をお迎えし、株式会社設立の経緯と理念、神楽坂で展開してきたプロモーション事業について、講演をしていただきました。文化事業のコンサルティングや神楽坂グッ
ズの企画開発、カルチャー教室の受託など、神楽坂を売り出す様々な事業を展開していることに驚かされました。
さらに、日本舞踊市山流家元の市山七十世氏、当会の大倉代表を加えたパネルディスカッションでは、古町花街の認知度を高め、もっと市民が花街を楽しめるようにするにはどうしたらよいか、意見交換がなされました。
また今回は、新潟シティガイドの協力による「古町花街めぐりボランティアガイド講座」の一部を兼ねており、シンポジウムに続き、シティガイド向けと一般参加者向けの2本立てで、花街講座と花街まちあるきが開催されました。当会会員や一般の方々に加え、多くのシティガイドの方々の参加があり、古町花街を活かしたまちづくりの輪が一段と広がる機会になりました。(今村洋一)
 |
| 写真はシンポジウムの様子。会場となった三業会館ホールには舞台があり、かつては芸妓の踊りが披露されました。 |
|
|
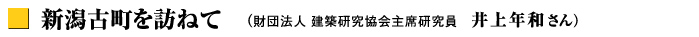 |
|
|
| 今回の花街イベントには、京都から、京都花街にお詳しい井上年和さんが参加してくださいました。古町花街の感想をお聞きしました。 |
普段は京都で文化財建造物の修復に携わっておりますが、ひょんなご縁で新潟大学の研究者の方々と花街研究をご一緒させていただいております関係で、シンポジウムとお座敷体験に参加させていただきました。
新潟へは初めての探訪でしたが、新潟駅から万代橋を渡り、信濃川沿いに旧県会議事堂まで歩き、その後も市内の文化財や町並みををぶらぶらと見学し、古町にたどり着きました。
古町は祇園東のようにお茶屋と雑居ビルが混在した状態と聞いており、雑然としたイメージを持っておりましたが、拝見いたしますと、適度に節度のとれた現代の盛り場という印象を受けました。
路地の中は古町独特の花街建築が多く残り、ネオンや厨房裏のダクトがあまり露出せずに清潔感があったことが私にとって魅力的な点でした。いざお座敷へあがらせていただくと、その設えやおもてなし、料理にも感激しましたが、振袖さんらによる舞は古町花街を最も特徴付けるものであると思いました。
古町には市山流日本舞踊が残されており、稽古を通じて舞踊という職能だけでなく、礼儀やしきたりを学びます。
 このような芸能は、元来神に捧げる神事が様々な変遷を経て現在に至るわけですが、日本人の感性や文化を伝え続けていく非常に重要な役割を果たしています。日本芸能が残されていることが節度と清潔感のある町並みに映し出されているのではないでしょうか。
このような芸能は、元来神に捧げる神事が様々な変遷を経て現在に至るわけですが、日本人の感性や文化を伝え続けていく非常に重要な役割を果たしています。日本芸能が残されていることが節度と清潔感のある町並みに映し出されているのではないでしょうか。
古町の花街文化が益々発展して、何度も古町を再訪したいと強く感じました。
写真は京都五花街のひとつ、上七軒の歌舞練場。舞妓の稽古場と舞台を備えています。↑
|
|
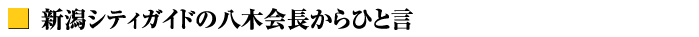 |
|
|
|
古町花街に残る建物の特徴についての具体的な説明を受け、さらに、まちあるきで実物を確認できたことが、大変参考になりました。学んだことを活かして、今では、お客様をガイドする際に、古町花街の建物の説明をさせていただいています。それぞれの団体が得意なところを活かし、協力しあえるようになってきたのは、大変よいことだと思います。(八木洋さん)
|
|
 |
|
●
|
|
やっぱりよくわからないのが「花街」。そこで、花街についての解説書で、入手しやすく内容もお勧めの本を何冊か選んでみました。
花街といえば京都。さまざまな本が出されていますが、ビジュアルな総合案内として、『京都花街』(光村推古書院、1,680 円)。花街の行事や舞妓さんの紹介がメインです。
京都の花街については、研究書ながら読みやすいものが2冊あります。
1冊は加藤政洋著『今日の花街ものがたり』(角川選書、1,575 円)。地理学者が京都の花街の成立過程を、祇園と島原を中心に解説しています。この著者の前著は日本各地の花街を調べたものですが(『花街』朝日選書)、まずは京都から。
京都花街解説書でもう1冊は、太田達・平竹耕三編『今日の花街 ひと・わざ・まち』(日本評論社、1,995円)。こちらは京都花街文化研究会という学際的な集まりから誕生した本です。特に、花街の建築や街並み保存について、それぞれ1章が割かれているので当会向きです。
次に、東京の花街案内書として、『東京六花街 芸者さんに教わる和のこころ』(ダイヤモンド社、1,680円)がビジュアルたっぷりで楽しめます。新橋、赤坂、芳町、神楽坂、浅草、向島が取り上げられています。副題にあるように、芸者さん紹介が主な内容です。
もう1冊は、浅原須美著『お座敷遊び 浅草花街 芸者の粋をどう楽しむか』(光文社新書、735 円)。浅草の箱屋(芸者さんの取次、荷物持ち、連絡などを請け負った業種)の半生のほか、浅草花街のさまざまな人々の紹介しながら、花街での楽しみ方を解説しています。(澤村明)
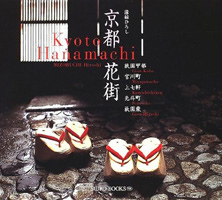 |
 |
 |
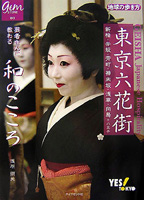 |
 |
| 『京都花街』 |
『今日の花街ものがたり』 |
『今日の花街 ひと・わざ・まち』 |
『東京六花街』 |
『お座敷遊び』 |
|
|
 |
|
|
|
当会も早いもので創設6年になります。
新潟の町屋、下町、西大畑、そして古町花街などを焦点に、新潟島を中心に町に残る歴史的な建物とその背景に光をあて、紹介する努力を続けて来ました。戦災を逃れた新潟が、実は歴史的建造物の宝庫であることが、次第に明らかになってきました。今後は新潟島外の地域にも注目していくこと、そして会の出発点となった東厩島町の町屋解体部材(当会所有)を生かす方途を考えていくことなどを、大きな課題としたいと思います。
引き続き会員の皆様のご協力や支援を、お願い申し上げます。(大倉宏)
|
|
 |
|
|
「第5回新潟県まちなみネットワーク糸魚川大会」が10月2日(土)・3日(日)に、糸魚川タウンセンター
ヒスイ王国館で開催され、当会世話人も参加しました。大会は年に一度県内のまちなみ団体が顔を合わせる貴重な機会となっています。
2日のシンポジウムでは、JTB 常務取締役の清水愼一さんが講演「最近の観光潮流 まちなか観光、まち歩き観光」で、まちの掘り起こし、まち歩き、街並みの整備が観光につながると、観光サイドから語り、多くの提言をされました。
つづく第2部講演では、当会の岡崎篤行副代表が「糸魚川と上越のまちなみ」をテーマに、新潟市や下越とも異なる上越の町屋の特徴を説明しました。
第3部講演「世界ジオパーク 糸魚川のまち歩きの楽しみ方」では、糸魚川ジオパーク市民の会会長の久保雄さんが、町並みからヒスイまで、糸魚川のまちの魅力を飄々とした話しぶりで紹介してくださいました。
中心部に残る趣ある建物を40 軒以上も紹介した「糸魚川レトロ建物番付」も配布していただきました。
翌日はまちあるきが行なわれました。町屋が多く残るのが旧加賀街道の雁木通りです。かつては本陣で、新潟県最古の酒蔵の加賀の井酒造、創業300 年の老舗京屋、平安堂旅館など大きな建物があります。この街道と交わっているのが旧松本街道の白馬通り。「塩の道」で、ここにも歴史を伝える建物が点在していました。
商店街では「街なかコレクション」というイベントが行なわれている最中で、店内でヒスイや家に伝わる古いものが展示されていたのも一興でした。
めずらしかったのは、「マップタッチ」という音声ガイドシステムです。イヤホンのついたペン状のモノを借り、名所旧跡にマークがついているマップを一緒にもらいます。マークのある場所に来たときにマップ上のマークにペンでタッチすると、解説が流れます。箱形のイヤホンガイドはよくありますが、持ち歩くマップにタッチする、というところが面白いシステムでした。(千早和子)
 |
 |
| まちなみネット大会の帰りに寄った糸魚川市筒石の漁村。写真左の橋を渡ると、奥に上のような路地が続きます。海岸線に平行した路地に建ち並ぶ、木造三階建ての家屋は、海と山とに挟まれたせまい土地で暮らす知恵でしょう。 |
|
|
 |
|
|
柏崎市東本町の閻魔堂は、毎年6 月の縁日に開催される「えんま市」で親しまれています。明治29年に柏崎の名棟梁のよって建立された土蔵造りの本堂は市指定文化財になっています。
2007年の中越沖地震では、閻魔像や十王像などは無事だったものの、本堂は向拝(ごはい・拝殿の正面の屋根が張り出した部分。参拝する場所)が倒壊し、土壁や基礎、土台にも被害を受けました。今年から本堂の修復、向拝の再建が始まりました。
閻魔堂は檀家がありません。そのため、修復・再建費用に充てるための寄進を募っています。寄進は郵便振替で受け付けているとのことです。
|
寄 進 一口 5000 円(複数口でも)
振込先 00570-8-96611
加入者名 閻魔庵
発起人 閻魔堂責任役員代表 小栗 清作
閻魔堂住職 今井 徹郎
〒945-0051 柏崎市東本町2 丁目7-40
電話 0257-22-2911
|
|
|
 |
|
|
|
■一般会計
|
収入の部
|
|
支出の部
|
| 会費・寄附金 |
288,000 |
| 事業収入(マップ売上げ) |
242,740 |
| 参加費(大成助成金事業、資料代) |
22,000 |
| 参加費(撮影会、中央区助成金事業) |
17,000 |
| 旧齋藤家補助金預かり金 |
172,000 |
| 旧齋藤家より(立替分) |
92,790 |
| 貸出金返済(旧齋藤家より) |
50,000 |
| 利 息 |
373 |
| 前年度より繰越 |
1,474,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 支出消耗品 |
7,478 |
| 印刷費 |
3,280 |
| 通信費 |
93,383 |
| 賃貸料 |
15,000 |
| 会議費 |
10,300 |
| 交通費 |
880 |
| 謝礼(ポストカード用写真撮影代金) |
50,000 |
| 仕入れ(シンポで販売した書籍) |
29,360 |
| 振込手数料 |
3,357 |
| 手数料 |
500 |
| 部材保管費 |
20,000 |
| 大成助成金事業支出 |
720,498 |
| 中央区助成金事業支出 |
181,204 |
| 旧齋藤家補助金(預かり分) |
172,000 |
| 旧齋藤家の立替分(通信費) |
92,790 |
| 貸出金(旧齋藤家へ) |
50,000 |
| 次年度へ繰越 |
909,567 |
|
|
|
|
| 収入合計 2,359,597 |
|
支出合計 2,359,597 |
|
|
|
 |
|
|
この夏から半年をかけ、中越地方で古い建築のつくりを紐解いて、現場作業を通じて実地に建物を学ぶ民家塾を主催しています。
地域に散在する古い民家や土蔵をこのまま放置すれば、使い手がいなくなれば壊されるか、自然と壊れるのを待つ中でいずれ消滅する運命にあります。そんな中、古い建物に込められた先人の知恵を理解してもらうこと、そして学ぶことが伝統建築を大切にする気持ちを育み、根づかせることにつながり、地域の民俗遺産を守ると考えてのことです。
戦後60 年の間は、とくに高度経済成長の過程で、新しいもの、技術革新を経たものが上で、古いものは価値のないものといった風潮に満ち、経済の行き詰まり感のある今でさえ、スクラップ&ビルドの考え方は改まってはいません。
そのような中で対象建物にもよるが、連続講座形式で、古い民家の床をはずして調査をしたり、補修工事では、土壁の壁土を作ったり、小舞下地から壁を直したりといったワークショップと座学をセットで設けて行う民家塾。始まると異口同音に聞こえてくるのが、職人でなくても誰でもやればできるということ。
 難しいと思っていたこれらの建築技術が、きわめてローテクで、確かな技術を持つ人の指導があれば、未経験者でもつくり手入れすることができます。そして、簡単に壊すことの愚かさを知り、結いの協働作業の楽しさに気づくのです。
難しいと思っていたこれらの建築技術が、きわめてローテクで、確かな技術を持つ人の指導があれば、未経験者でもつくり手入れすることができます。そして、簡単に壊すことの愚かさを知り、結いの協働作業の楽しさに気づくのです。
|
|
 |
|
|
花街マップはもうほとんど在庫がありません。現在改訂版を作成中で、来春までには改訂版を発行する予定です。
* * * * * * * * *
毎月第2火曜日の6時半から、西堀の市民活動支援センターで世話人会を開き、会の活動について話し合っています。お気軽にご参加ください。日時は変更する場合がありますので、事務局にご連絡ください。
|
|
 |
|
■ 会報バックナンバー
vol. 1 / vol.2 / vol.3 / vol.4 / vol.5 / vol.6
vol.7 / vol.8 / vol.9 / vol.10 / vol.11 / vol.12
|
|
|
  |

